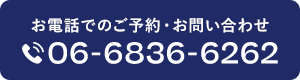冷え性とは?
「手足が冷たい」「布団に入ってもなかなか温まらない」「エアコンの効いた部屋にいると体調が悪くなってしまう」といったお悩みを感じている方は、冷え性かもしれません。
冷え性とは体の末端や全身が冷たく感じる状態のことを言います。冷え性は単なる体質と思われがちですが、身体が冷えることで血流や自律神経系、ホルモンの乱れなどが生じてしまうことがあり、放置していると肩こり、頭痛、月経不順、不眠、胃腸障害などの症状を引き起こします。
本来は、外気温に合わせて血管を拡げたり縮めたりして体温を一定に保とうとしています。この体温調節を司っているのが自律神経系です。しかし、ストレス・睡眠不足・不規則な生活などの要因で自律神経系が乱れてしまうと、血流が悪化し、特に手足などの末端部分まで十分な血液が行き届かなくなることで冷え性が生じます。
冷え性の主な原因
冷え性の原因は1つではなく、いくつかの要因が複合的に関わっています。
血行不良
長時間のデスクワークや運動不足によって筋肉量が低下していくと血液を全身に送り出す心臓の機能が弱まり、末端の血流が滞ってしまいます。
自律神経の乱れ
過度なストレスや生活リズムが乱れることで交感神経が優位になり、血管が収縮してしまいます。体が常に緊張した状態となり、冷え症を悪化させます。
ホルモンバランスの変化
女性は月経周期、更年期などの影響でホルモンバランスが変動しやすいです。そのため、血流や体温調節も乱れてしまいます。冷え性は圧倒的に女性に多いです。
低血圧・貧血
血圧が低い方や血液中にある赤血球が少ない方は、体の隅々まで血液を運ぶ力が弱いため、冷えを感じやすくなります。
甲状腺機能低下症などの疾患
基礎代謝を下げてしまう病気(甲状腺機能低下症、糖尿病、自律神経失調症など)が生じていると、体全体の代謝が落ちてしまい冷えが強くなります。
冷え性に伴う症状について
- 手足の冷え、しびれ
- 肩こり、頭痛
- 便秘、下痢などの消化器症状
- 月経痛・月経不順
- 不眠、倦怠感
- むくみや肌の乾燥
冷え性の検査
慢性的に冷え症が続く場合は、単なる体質と片付けずに医療機関での検査を受けるようにしてください。血液検査で貧血や甲状腺機能、血糖値を確認したり、血圧・自律神経機能の評価を行うことで、背景に何かしらの病気が隠れていないかを検査していく必要があります。
冷え性の治療に向けて
-
普段の生活習慣の改善
・身体を温める食事を意識
ショウガ、ネギ、にんにく、根菜類などの温性食材を積極的に食べるようにしましょう。冷たい飲み物や生野菜の摂りすぎは控えめにしてください。
・適度な運動を継続
ウォーキングやストレッチなど軽い運動でも血流を促進してくれます。特にふくらはぎの筋肉を動かすことが重要です。
・規則正しい生活リズム
睡眠不足は自律神経系のバランスが崩れてしまいます。早寝早起きを心がけ、ストレスを溜めない工夫をしましょう。
-
スキンケア・衣服の工夫
下半身を冷やさないように、靴下や腹巻き、レッグウォーマーなどを利用することも効果的です。衣服は重ね着で体温を逃がさない工夫をしてください。ただし、締め付けの強い服は血行を妨げますので注意してください。
-
医学的治療
・内服薬
血流を改善するビタミンE製剤や漢方薬(当帰芍薬散、桂枝茯苓丸など)を使用することがあります。
・基礎疾患の治療
甲状腺疾患や貧血がある場合は、その治療を行うことで冷え症が改善することがあります。
漢方薬によるアプローチ
冷え性の治療では、体質に合わせた漢方治療も有効となります。漢方治療を行っていく際は体質に応じて漢方薬を選びます。医師の診察のもとで適切に用いるようにしてください。
- 当帰芍薬散:冷え性でむくみや生理不順を伴う女性に効果的です。
- 桂枝茯苓丸:血流が悪く、手足の冷えと肩こりを伴う方に効果的です。
- 八味地黄丸:下半身の冷え、頻尿、腰痛がある高齢者に効果的です。
冷え性と女性の健康
女性は男性に比べて筋肉量が少なく、ホルモンバランスの影響も受けやすいため冷え性が多くみられます。特に月経痛やPMS、更年期症状と冷え症は関連しています。血流を整えることで月経トラブルの改善にも繋がることもあります。
放置しないことが大切
冷え性を放置すると、慢性的な肩こりや頭痛だけでなく、代謝の低下による太りやすさ、肌荒れ、免疫力の低下にもつながっていきます。「冷えは万病のもと」と言われるように、早めに対処することで心身の健康を守ることができます。
冷え性については単なる体質ではなく、普段の生活習慣や体の不調のサインとしてとらえることが大切です。『血流を良くする』『自律神経を整える』『食事と運動で基礎代謝を上げる 』ことを意識し、冷え症に強い体づくりが大切です。
改善しない場合や、全身のだるさ・低体温・月経異常を伴うときは、内科での診察を受け、必要に応じて血液検査やホルモン検査を行いましょう。些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談してください。