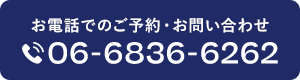脳卒中とは
 脳卒中とは、脳の血管が詰まる、破れるといったことで、脳に障害をきたす病気の総称です。
脳卒中とは、脳の血管が詰まる、破れるといったことで、脳に障害をきたす病気の総称です。
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などが挙げられます。いずれも、重い後遺症が残ったり、命が危険にさらされたりすることのある病気です。
脳卒中の3つのタイプ
脳卒中は大きく血管が詰まる「脳梗塞」、血管が破れて出血する「脳出血」、「くも膜下出血」の3つのタイプに分けられます。
脳梗塞
脳出血
くも膜下出血
脳卒中の症状
以下のような症状がある場合には、脳卒中が疑われます。
- バットで殴られたような強烈な頭痛
- 身体の片側の麻痺、しびれ
- 呂律が回らない
- 言葉が出にくい
- 視野欠損、物が二重に見える
- グラグラとし歩けないようなめまい
- 視認している物をうまく手に取れない、伸ばした手が通り過ぎてしまう
- 意識障害
- 字や直線が書けない、箸が正しく使えない
脳卒中の原因
脳卒中に共通する原因に、動脈硬化があります。そしてその動脈硬化を引き起こすのが、高血圧、脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病です。
くも膜下出血の場合は、何らかの原因で脳動脈瘤が発生し、ここに高血圧や動脈硬化といったリスクが重なることで、破裂します。
脳卒中の疑いがあればすぐに救急車を
 脳卒中が疑われる症状が起こったときには、「もしかしたら違う病気かもしれない」という迷いは捨て、救急車を呼んでください。
脳卒中が疑われる症状が起こったときには、「もしかしたら違う病気かもしれない」という迷いは捨て、救急車を呼んでください。
たとえ一時的に症状が軽快しても、重い脳梗塞の前兆だったというケースも少なくありません(一過性脳虚血発作)。
命を救える可能性を残すため、そして後遺症を少しでも軽いものにするためには、迅速な対応と適切な治療が不可欠です。
冷え症とは
 「冷え性」とは、検査などで特別な異常が認められない一方で、手足の末端や体の全体が冷えていることを指します。手足が冷えるタイプを四肢末端型、全身が冷えるタイプを全身型などと呼びます。
「冷え性」とは、検査などで特別な異常が認められない一方で、手足の末端や体の全体が冷えていることを指します。手足が冷えるタイプを四肢末端型、全身が冷えるタイプを全身型などと呼びます。
身体が冷たいために日常生活に支障をきたすだけでなく、他の身体の不調を招くこともあります。冷え性は、治療により改善が可能です。
「冷え性」と「冷え症」は違う?
冷え性と同じ読み方で、「冷え症」というものがあります。
冷え症は、冷え性とは異なり、検査で異常が認められる状態であり、何らかの疾患が原因になっていることもあります。
一方で冷え性は、検査で異常のない、病気を原因としない、体質のことを指します。
冷え性の種類
冷え性には、以下のようにいくつかの種類があります。
四肢末端型冷え性
手足の末端が冷たいタイプです。
若い世代で、無理なダイエットを原因として引き起こされるケースが目立ちます。
肩こりや頭痛を合併することがあります。
全身型冷え性
全身が総じて冷たいタイプです。
加齢に伴う筋肉量の低下が原因になるケースが目立ちます。
倦怠感や下痢、抵抗力の低下などが見られることがあります。
下半身型冷え性
下半身全体が冷たいタイプです。
長時間のデスクワーク、運動不足、不良姿勢などによって下半身の血流が低下することが主な原因です。
内蔵型冷え性
内臓が冷えるタイプです。
不規則な生活リズム、ストレス、睡眠不足などによって自律神経が乱れ、引き起こされるケースが目立ちます。
体表の冷えが感じられないため、なかなか気づけません。下痢や倦怠感などを伴うこともあります。
冷え症に悩む男性も増えています
冷え性で悩む人の男女比を比べると、女性の方が多くなります。卵巣や子宮があることによって男性よりも腹部の血流が良くないこと、月経による血液不足・ホルモンバランスの変化があることなどが要因で、こういった性差が認められます。
ただ、冷え性はそれ以外にもたくさんの要因を持ちます。そのため、冷え性に悩む男性も少なくありません。特に近年は食生活の乱れや長時間のデスクワーク、運動不足、エアコンによる室内と外の気温差などで、冷え性にお悩みになる男性が増えてきています。
冷え性の原因
冷え性の原因は、実に多様です。多くは、複数の原因が影響して、冷え性が引き起こされます。
筋肉量の低下
加齢や運動不足は、筋肉量の低下、またそれに付随して血流の低下を招きます。
特に、ふくらはぎの筋肉は下肢の血液を心臓に向けて送り出すポンプの役割を担っているため、その筋肉量の低下は、冷え性の重大なリスクとなります。
基礎代謝の低下
運動不足などによって基礎代謝が低下すると、身体に脂肪が溜まりやすくなります。脂肪というと身体を温めてくれそうですが、筋肉のように血流を促進することがないため、冷え性を引き起こしやすくなります。
食生活の乱れ・無理なダイエット
ミネラルやビタミンの不足は、冷え性を引き起こす原因になります。
また食事を摂らない・極端に減らすといった無理なダイエットは、栄養の不足や筋肉量の低下を招き、やはり冷え性の原因となります。
自律神経の乱れ
不規則な生活リズム、ストレス、睡眠不足などによって自律神経が乱れると、体温調節が適切に行われなくなり、冷え性を引き起こす原因になります。
また胃腸などの内臓の機能も低下し、やはり冷え性の原因となります。
性別(女性)
女性は、卵巣や子宮があることで、男性よりも腹部の血流が悪くなりやすいと言われています。また月経、妊娠、出産、閉経などのタイミングで生じるホルモンバランスの乱れも、冷え性の原因の1つとなります。
薄着・衣類の締め付け
薄着はもちろん、血流を悪化させるような締め付けの強い服を日常的に身につけることは、冷え性のリスクを大きくします。
衣類は気温・室温に合わせて小まめに脱ぎ着し、締め付けすぎないものを使いましょう。特に下着や靴下などにおいて、締め付けるものを使用してしまっているケースが目立ちます。
冷え性の治療と改善方法
冷え性は、治療により改善が可能です。ご自宅で取り組んでいただけることもありますので、まずはお試しください。
治療方法
 クリニックで行う治療は、薬物療法が中心となります。
クリニックで行う治療は、薬物療法が中心となります。
西洋薬として、末梢の血流を改善したり、ホルモンの分泌を促進する「ビタミンE」を配合した内服薬を主に使用します。
当院では、漢方治療も積極的に行っております。患者さんの症状・体質・体力・抵抗力などに合わせて漢方薬を処方いたします。冷え性に対しては、以下のような漢方薬を使用します。
人参養栄湯
消化吸収を助ける生薬、滋養強壮作用のある生薬、血流を改善する生薬を含みます。
全身が冷えるという方に使うことが多くなります。
八味地黄丸
滋養強壮作用のある生薬、血流を改善する生薬、身体を温める生薬が含みます。
下半身が冷えるという方に使うことが多くなります。
桂枝茯苓丸
血流を改善する生薬を含みます。
下半身が冷える一方で、顔面はほてるといった方に使うことが多くなります。
加味逍遥散
自律神経のバランスを整える生薬、血流を改善する生薬を含みます。
自律神経の失調に伴う冷えやのぼせなどがある方に使うことが多くなります。
当帰芍薬散
血流や貧血を改善する生薬、身体を温める生薬、むくみを改善する生薬などを含みます。
水分の代謝が低下し、手足など末端が冷える方に使うことが多くなります。
当帰四逆加呉茱萸生姜湯
血流を改善し、身体を温める生薬を含みます。
手足が冷え、しもやけがよくできる方に使うことが多くなります。
改善方法
食習慣の見直し
 栄養バランスの良い食事を前提とし、特にミネラルとビタミンを意識的に摂取しましょう。
栄養バランスの良い食事を前提とし、特にミネラルとビタミンを意識的に摂取しましょう。
血流の改善、身体を温める栄養素・食品をご紹介します。
ミネラル
亜鉛、マグネシウム、鉄などのミネラルは、身体を温める作用があります。
| 多く含まれる食品 | |
|---|---|
| ビタミンC | 柑橘類・緑黄色野菜・いちごなど |
| ビタミンE | アーモンド・うなぎ・ピーナッツ・卵黄など |
| ビタミンB1 | 肉・大豆・卵・魚類・豆類・穀類など |
パントテン酸
代謝を促進し、自律神経のバランスを整える作用があります。
| 多く含まれる食品 | |
|---|---|
| パントテン酸 | 大豆・カリフラワー・鶏レバー・鶏ささみ・卵・魚類・牛乳・豆類など |
タンパク質
良質なタンパク質は、重要なエネルギー源となり、神経機能を正常に維持するのに役立ちます。
| 多く含まれる食品 | |
|---|---|
| タンパク質 | 大豆製品・魚類・肉類・牛乳・乳製品・卵類など |
運動習慣の見直し
 運動習慣を身につけることで、筋肉量の維持・増大、血流の改善の効果が得られ、冷え性の改善に繋がります。
運動習慣を身につけることで、筋肉量の維持・増大、血流の改善の効果が得られ、冷え性の改善に繋がります。
ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動がおすすめです。軽く汗をかくくらいの強度で構いません。
筋力トレーニングでは、下肢の筋肉を鍛えることが有効です。壁に手をついてかかとの上げ下げをする方法では、手軽にふくらはぎの筋肉を鍛えられます。
その他
 規則正しい生活を送ること、睡眠を十分に摂ること、ストレスを解消することで、自律神経のバランスを整えましょう。
規則正しい生活を送ること、睡眠を十分に摂ること、ストレスを解消することで、自律神経のバランスを整えましょう。
胃腸の調子が改善したり、ホルモンの分泌が促されたり、体温調節が適切になされることで、冷え性の改善に繋がります。